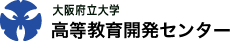教職員インタビュー
category
第5回 教員インタビュー 前川 真行 先生
| 2014年3月25日(火) |

地域連携研究機構 前川 真行 准教授
こんにちは。工学域物質化学系学類応用化学課程3回生の高松晃彦です。
以前森岡正博先生に科学技術が発達した現代社会について倫理の観点からお話を伺いました。その後頭の中には「科学技術と社会」というキーワードが強く頭に残りましたが、扱う問題の規模が大きすぎてどうすればさらに考えを進められるか分からず立ち止まっていました。
そこで後期の教養ゼミナール「経済から社会を見る」の担当教員であった前川真行先生に科学技術と社会の関係について勉強するにはどのような本を読めばよいか教えていただきました。紹介いただいたのが『科学者に委ねてはいけないこと――科学から「生」をとりもどす』『ポスト3.11の科学と政治』『科学の社会史』の三冊でしたが、どの本も個別の事例について深く書いてあり科学技術と社会の問題に関する全体像を掴むことができませんでした。また、「私一人が科学技術と社会のあるべき関係を考えても、私は巨大なシステムの中で生きる一つの歯車のような存在であり、社会の中で一人が何かを考えることに意味は無いのではないだろうか?」というニヒリズムに陥ってしまい、考える気力も薄れてしまっていました。
そこで問題の全体像を教えていただきたいと思い、先生にお話をお伺いすることにしました。
➡ 社会思想史を専攻された理由を教えていただけませんか?
➡ 一人の人間が科学技術と社会のあるべき関係を考えても、その考える人は巨大なシステムの中で生きる一つの歯車のような存在であり、意味は無いのではないでしょうか?
➡ 学生へのメッセージをお願いします
➡ インタビューを終えて(学生スタッフより)
| 社会思想史を専攻された理由を教えていただけませんか? |
私は数学が割とよくできたので、理系と文系が両方できるのではないかと考えて経済学部に入りました。それなのに、当時大学生の頃に現代思想ブームがあり、たまたま通っていた大学がブームの発信地でして、不幸なことにあのころの現代思想と呼ばれていたものはとてもセクシーに見えたのですね(笑)。若い頃は往々にして愚かですから、ついつい面白いと思ってしまい、気がつくと社会思想史を専攻することになっていました。皮肉なことにこれはセクシーさのかけらもない古くさいスタイルの学問です。人生を間違えたと言わざるをえません。
| 一人の人間が科学技術と社会のあるべき関係を考えても、その考える人は巨大なシステムの中で生きる一つの歯車のような存在であり、意味は無いのではないでしょうか? |
■『期待される人間像』を手掛かりに
それは現代を生きる人間にとって普遍的な問いと言えるでしょう。例を挙げると高度経済成長期、1960年代に文科省の中央教育審議会が書いた『期待される人間像』の解説を高坂正顕(注1)という人が書いたのですが、その解説には次のようなことが書かれています。
・今日新たな人間像が期待されるのは現代社会に生きる人間の人間像の分裂、さらにはその喪失に深い根拠がある。
・現代文明の一つの特色は自然科学の勃興にある。これが人類に多くの恩恵を与えたことは言うまでもない。医学や産業技術の発展はその恩恵のほどを示している。
・産業技術の異常な発達は機械が逆に人間を拘束する危険性を示してきた。
・人間性を高めつつ人間能力を高めよ
・世界に開かれた日本人であれ
・健全な民主主義を自立せよ
・機械を支配する人間であれ
・大衆文化、消費文化に溺れるな
(注1) 日本の哲学者。文学博士。専門は、カント哲学。京都学派の一人。
■機械に支配される人間
実は当時、この本は進歩的な若者たちに復古調だと批判されたものですが、よく読むと、主題は科学技術論なのですね。しかもこの本を批判した側とわりあいと共通点が多い。要するにチャップリン(注2) の『モダン・タイムス』のように人間が機械に支配されてしまうことへの恐怖のようなものです。その背景にあるのは、核兵器と原子力発電所、つまり原子力エネルギーの衝撃だと思います。人間が使えるエネルギーの大きさは人力、馬力、水力、石炭、石油、原子力と時間を重ねるごとに、技術の発展とともに大きくなってきました。原子力のように莫大なエネルギーが果たして人間にコントロールできるのか、という疑問は昔から唱えられてきました。人間にできることが非常に大きくなってしまう。やはり当時としては冷戦下で核兵器が念頭にありましたから、人間が自ら作った技術で人類を、地球を滅ぼしてしまうのではないかという懸念がありました。アレント(注3) という哲学者や、大江健三郎 (注4)はそのような恐怖を同時代的に抱きながら当時を生きました。大江健三郎の『ピンチランナー調書』という小説があります。その小説に主人公と重要なかかわりを持つ登場人物で原子力発電所の作業員が出てくるのですが、彼は原発反対運動のテロに遭い、致命的な結末を避けるために彼一人が深刻な被ばくをしてしまいます。彼はその後結婚をするのですが生まれた子供に障がいがありました。恐らく障がいと被ばくの因果関係は無い、というよりはおそらくは証明できないことが示唆されてはいるのだけれども、しかし彼と彼の家族にはなんとも割り切れないものをあとに残してしまう。いま読んでもこの小説は3.11以後のことを予告するかのような、とても複雑な構成になっています。つまりこれはかならずしも原子力発電所が生命に影響を与えるということを書いているのではないのです。むしろここで主題になっているのは、おなじlifeでも生活や人生という範囲の問題です。これはいったんは腑分けして考えるべき問題です。
(注2) イギリスの映画俳優、映画監督、コメディアン、脚本家、映画プロデューサー、作曲家。
(注3) ドイツ出身の哲学者、思想家。アメリカ合衆国に亡命。主に政治哲学の分野で活躍した。
(注4) 日本の小説家。1994年にノーベル文学賞を受賞。
(注5) 古代ギリシアの哲学者。『ソクラテスの弁明』や『国家』等の著作で知られる。
社会における政治的決定と科学の関わりをいったん相対化する必要があると思います。もちろん科学がそこに関与することによって生じる固有の問題はあるのですが、科学技術のイメージを最初から限定してしまうことで、見えにくくなっている部分もあると思います。
(注6) ドイツの哲学者。『存在と時間』等の著作で知られる。
■民主主義を考える
現代社会を考えるうえで民主主義は避けて通ることができません。大阪市長選挙がありましたが、直接選挙制で選ばれた市長は民意を全て反映していると言えるのか。あるいはまた、間接選挙制で選ばれた議員が集まる議会は何をする場であるのか。たとえば議会において為されるべきことはdeliberationであるとフランス革命において言われました。むかしは審議と訳されていましたが、ちかごろは熟議と訳す人もいます。debateは賛成派と反対派の二つに分かれて勝ち負けを決めますが、deliberationには勝ち負けがなく、よりよい妥協点を見つけることが目的とされます。だから、議員は本来公約に縛られないはずなのです。そこには旧体制の、フランス革命以前の議会らしきものでは職人団体(組合)や地域、さまざまな身分の利害関係をぶつけ合うだけで生産的な議論はされていなかったのではないかという反省があるわけです。命令的委任といいますが、話し合いの場にいる人は選出母体の意思決定を覆すことはできなかったために妥協が不可能だったからです。近代的な議会では、自らの属する共同体の利益と議論をいったん切って考えるのです。民主主義の代表者を選出するという過程は義務、とまでは言いませんが理念的には全ての市民に与えられた役割です。
■倫理、合意形成を考える
科学技術に特有の問題、つまり倫理の形成をどうするのか。突き詰めると合意形成はどうなるのか、という問題になると思います。ある社会における専門家とそうでない者の間にある溝をどう埋めるのか。遡って考えると政治における直接民主制と間接民主制の問題、つまり政治を行うのは民衆か貴族か(血によって選ばれるのであれ、能力によって選ばれるのであれ、人間性のようなもので選ばれるのであれ)という問いですね。例えば、非常に簡単な操作で生命の加工ができる技術が新しく出来たとします。すると、生命の倫理を守るために先進国でルールを定めて研究を行っても発展途上国においてルールが破られてしまう事態は避けられないでしょう。新しい技術が生まれた場合、その技術によって人間に何ができるようになり、また社会にどれほどの影響を与えるのかということを考えなくてはいけない。科学技術と社会という一つの問題があるわけではなく、問題を腑分けしていき考えられるところから手を付けていくしかないでしょう。腑分けされたことが全体の中にある一つのことだと忘れないようにすることは必要ですが。
■専門家支配について考える
科学技術と社会の関係について解答という形で与えることはできないと思いますが、考えていくうえでの道筋のようなものは準備出来るのではないか、と思います。科学技術が介在することで生じる固有の問題、いわゆる専門家支配の問題、民主主義の問題、とこのように腑分けして考えることだけでも、多少は見通しは良くなると思います。もはや専門家なしには社会は運営できないようになってしまっている。現実には専門家支配はもう避けられない(このとき「支配」という言葉の意味はとても複雑ですが、いまは措いておきましょう)。ならば、どうするのか。どうやって破綻することなくそのシステムを運営していくのか。専門家の知識をどのように共有するのか、どこまで共有するのか。すべてを共有することはできません。時間は限られていますからね。ある一定水準の専門知識を身につけるためにどれくらいの時間が必要なのかは、実際にやってみなければ分からないでしょう。専門家をどのように信頼すればよいのか。また、専門家の責任も問題にあがってくると思います。何をどうすれば責任を取ったことになるのか。何かをすることで負債がキャンセルされるような仕組みを作るのか。また、どうすればその仕組みはたくさんの人に受け入れられるのか。考えられる所までは、考えなければいけません。
| 学生へのメッセージをお願いします。 |
学生「全体」へ向けたメッセージは無いですね。やはり大学ですから、勉強してください(笑)。大学で得られるのは専門的な知識への手掛かりくらいですが。一般論よりも、個別の関係で誰かと何かを話す機会はあったほうがいいのかもしれません。
| インタビューを終えて(学生スタッフより) |
先生にインタビューのお話を伺うまでは自分の問題意識が混沌としており、何を考えればよいのか分からず一歩も前に進めない状況でした。しかし先生のお話を伺い、腑分けして考えることでまだ見通しは良くなることが実感できました。専門化が進展した社会を生きるうえでそれでもこの問題の奥は深く、やはり一人一人が時間の許す限り問題意識を広く持ち勉強し、問題について考え身近な人と議論していくことが必要だと思いました。何故なら、大きな問題について考えることは一朝一夕にはできないからです。
それに、科学技術と社会の関わる問題について完全な解答を描くことは難しくてもある段階までは考えを進められると思います。問題意識を忘れずに常に頭の隅に置いておくことが技術開発という仕事の意味、新しい技術が人々と社会に与える良い影響や悪い影響を考えるうえで大切だと思います。
また私が痛感していることは、自分で考えることはたくさん本を読んだ後に初めて可能になるということです。先人が考え抜いて見えてきたものの一部を借りてようやく一歩先に進める、という感じです。人文系の先生の研究室にある本が数えきれない程あることにも納得します。1960年代と現代が分業の進展した時代という視点で見ると通じていました。現代の問題と同じ構図の問題が過去の歴史の中にあり、過去のその時代に生きていた人が考えたことを再び考え直すことで問題の本質に迫ることが出来ます。
知とは本来何なのか。言葉とは一体何なのか。自然とはどのようなものなのか。そのような眩暈がしそうな大きな問いを、工学的、解析的なアプローチではなくただ言葉を紡ぐことによってその本質に迫っていくことができると私は信じています。そう信じさせるのは考えに考え尽くした人が見つけた言葉たちです。ある表現を読んだ時に100%分かったとは言い切れない、しかし全く分からないわけではない、その0と1の間にしか存在しない表象はあると思います。
やはり科学を志す人間は科学が一体どんな営みなのかを知り、自分のやろうとしていることがどのような意味を持つのか問い直し続けなければならないと思います。人文学という大きな学問は、科学を外から捉えることを可能にすると思います。問い直すことで科学の持つ新しい側面が見えてくることがあると思います。
 科学者が自らのやることについて自覚的にならなければ、ただ科学者コミュニティの外から批判されても真にその意味を把握し、問題を解決していくことは出来ないと思います。
科学者が自らのやることについて自覚的にならなければ、ただ科学者コミュニティの外から批判されても真にその意味を把握し、問題を解決していくことは出来ないと思います。
ですがもちろん、今回のインタビューで前川先生がお話ししていただいたように漠然としたイメージで語るのではなく、分析的に考えていくことも大事であることを掴みました。
諦めたらそこで終わってしまうので、長期的なスパンを視野に入れて自分の見取り図を作っていきたいと思います。